
この記事は3分で読めます







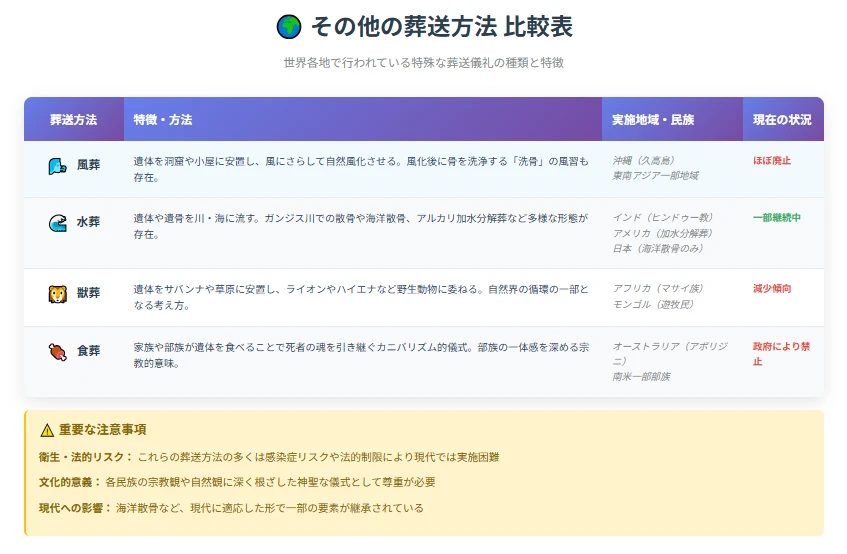
鳥葬とは何ですか?
鳥葬は、亡くなった人の遺体を自然に還すための葬送方法です。特にチベットやゾロアスター教の地域で行われています。遺体を山の上に置き、ハゲワシが食べることで自然の一部として循環します。
日本で鳥葬を行うことはできますか?
日本での鳥葬は法的に認められていません。日本の「墓地埋葬法」や「刑法190条」により、遺体を野外に放置することは許されていません。土葬や火葬には市区町村の許可が必要であり、鳥葬はこれに該当しないため実施が難しいです。また、ハゲワシなどの鳥を用意することも現実的に困難です。
鳥葬を見学することはできますか?
現在、チベットでの鳥葬の見学は厳しく規制されています。過去には一部地域で観光客向けの見学が許可されていましたが、文化的価値を保護するために禁止されました。特に、死者の尊厳を守るために撮影や録音も制限されています。鳥葬は神聖な儀式とされ、外部の人が立ち入ることは不適切と見なされるためです。
鳥葬とはどのような葬儀方法ですか?
鳥葬とは、遺体を野外に置き、鳥類により遺体を処理してもらう葬儀方法です。主にチベットやモンゴルなどで行われており、遺体を自然に還す意味があります。
鳥葬はどの国や宗教で行われていますか?
鳥葬は、主にチベット仏教やゾロアスター教を信仰する地域、特にチベットやモンゴルなどで行われています。
日本で鳥葬を行うことは可能ですか?
日本では、法律上、鳥葬を行うことは認められていません。火葬や土葬が一般的な葬送方法として定められています。
鳥葬は見学することができますか?
鳥葬は神聖な儀式であり、観光目的での見学は控えるべきとされています。特にチベットでは、無節操な観光客が増えたことから、厳しい取り締まりが行われています。
鳥葬が行われる背景や理由は何ですか?
鳥葬が行われる背景には、土地の地理的条件や宗教的信念があります。例えば、チベットでは土葬が難しい地形であり、また、遺体を鳥に食べてもらうことで魂が天に昇ると信じられています。
鳥葬は現代でも行われていますか?
現代でも鳥葬は行われています。チベットの一部の地域では鳥葬が行われており、時々テレビのドキュメンタリーなどでも放送されています。しかし、価値観や文化の変化から鳥葬を行う数は減少傾向にあります。

葬儀の人材派遣と集客支援の最大手、株式会社ディライトの代表取締役。20歳で葬儀の人材派遣スタッフとして働き始め、独立。以降約20年間、葬儀業界の「人の困った」と「集客の困った」を解消し続けている。

Amazonランキング 冠婚葬祭・マナー部門1位獲得
Amazonランキング
冠婚葬祭・マナー部門1位獲得
クロスメディア・パブリッシング(インプレス) (2025/5/30)
もしもの時に後悔しない選択をするために 葬儀とお墓選びで多くの方が失敗する落とし穴を徹底解説 国内最大手の葬儀社&お墓の口コミサイト 「葬儀の口コミ」「お墓の口コミ」運営社代表による、 損しないために知っておきたい、葬儀・お墓の基礎知識