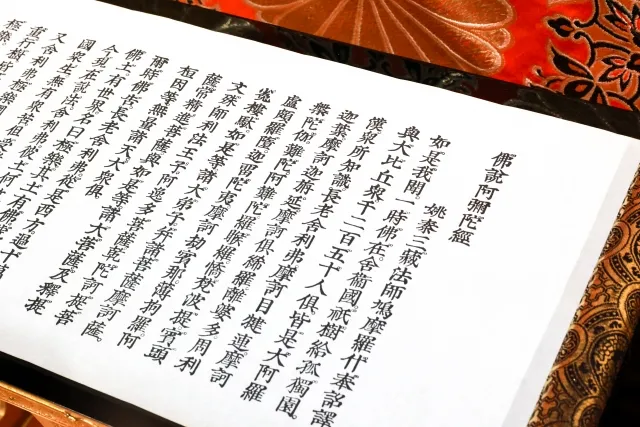| 教え | 意味・内容 |
|---|---|
| 只管打坐 | 「ただひたすらに坐る」こと自体が修行であり悟りであるという考え |
| 修証一如 | 修行と悟りは本来ひとつであるという教え |
曹洞宗は、坐禅にひたすら打ち込む「只管打坐(しかんたざ)」を説くのが特徴の宗派です。
ここでは、以下3つの観点から曹洞宗について解説します。
・坐禅そのものを目的とするのが曹洞宗の基本
・日常のすべてが修行であり悟りである|曹洞宗の修証一如
・曹洞宗の開祖道元と瑩山
曹洞宗はそのシンプルさから、哲学者の和辻哲郎やAppleの創業者であるスティーブ・ジョブズに影響を与えたと言われています。
世界的な成功者に影響を与えた宗派の教えをチェックしていきましょう。