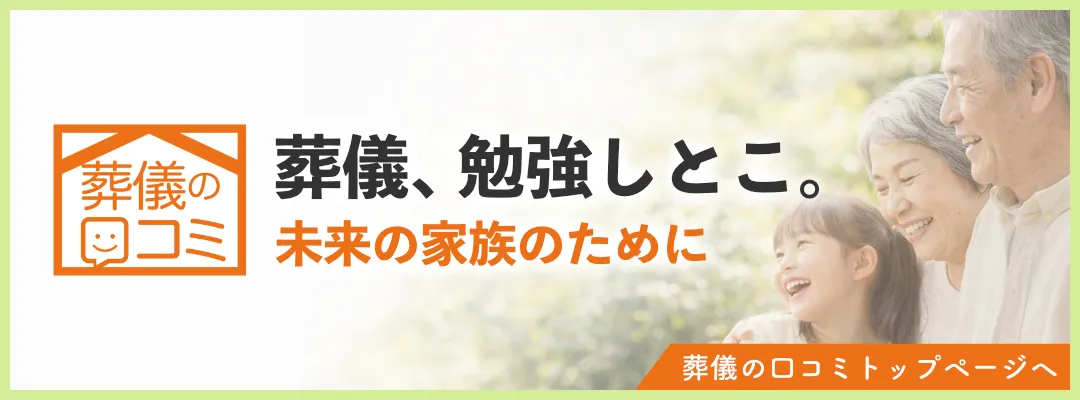| 悼む(いたむ) | 弔う(とむらう) | 偲ぶ(しのぶ) | |
|---|---|---|---|
| 意味 | 死への悲しみと嘆き | 故人の哀悼と供養 | 故人を懐かしく思い出す |
| 使う時期 | 訃報を聞いた直後 | ・葬儀 ・告別式 | ・通夜
・偲ぶ会 ・葬儀後 ・法要 |
| よく使う表現 | 「心から悼みます」 「深く悼んでおります」 | 「謹んで弔います」 「故人を弔う」 | 「故人を偲んで」 「在りし日を偲ぶ」 |
「悼む」:死に対する悲しみと嘆きを表し、感情を表す言葉です。追悼式や悼辞などで使われます。
「弔う」:葬儀や法要といった儀式を通じて、死者の霊を慰める行為を指します。公式な場で使用されるのが一般的です。
「偲ぶ」:故人との思い出を懐かしむニュアンスが強い言葉です。故人だけでなく過去の出来事や人柄にも使えます。偲ぶ会など、自由な形式での集まりで使われる場合が多いです。
「悼む」は悲しみの感情、「弔う」は儀式としての供養、「偲ぶ」は追憶と懐かしさを表すのが一般的です。